共産党を拒絶するナショナルセンター労組「連合」が保守与党の自民党に接近し、小党分立した野党陣営の選挙協力を阻み、事実上の一国一党体制ができつつある。今夏の参院選を皮切りに今後の国政選挙では自公与党が長期的に圧勝を続ける態勢が整った。現下のウクライナ危機や中国、北朝鮮の動向を巡る脅威扇動で、防衛費大幅増と米国及び西太平洋に再進出した英国との軍事連携強化を是とする「国民的コンセンサス」が出来上がった。この合意を生んだのが選挙権、労働者の団結権やスト権、言論、表現の自由をはじめ民主主義の基本的諸権利を次々とかなぐり捨て新たな翼賛体制の形成に向かう日本人の大勢順応・同調体質である。戦勝国米英豪は日本との軍事連携を進める一方で潜在脅威とみなす日本を厳格に管理しながら、中国、ロシアと対決するための尖兵として利用している。日本人はアングロサクソンの掌で踊らされながら鬼畜米英を悪魔中露へと挿げ替えた。
■不作為型翼賛体制の構造
第二次大戦突入の流れの中で形成された総動員・翼賛体制は敗戦を機に日本を単独占領した米国に付与された民主主義体制によって清算されただろうか。答えは否である。民主主義の諸権利を積極行使する不断の努力とは真逆の、なすべき諸権利を行使しない不作為が今日の日本を翼賛体制へと限りなく近づけている。その原動力として清算されることなかった家父長型集団主義統制が挙げられる。
1946年から1960年ごろまでの高度経済成長期前に生まれた戦後第一世代は日本国憲法に謳われている平和主義、基本的人権、主権在民と民主主義の重要さを主に教室で教わった。すべての人が徴兵もなく、戦禍もない幸運、そして多くの人がかつてない経済的豊かさを享受した。過半の人々は、明確な自覚はないにせよ、これを平和憲法を基盤とする戦後民主主義の恩恵と勤勉な国民性の賜物と受け止めた。戦争体験者には「自由にものが言える、良い世の中になった」と語る者が少なくなかった。だがこの民主主義は受動的な恩恵だっただけにその何たるかが人々の心に深く刻まれることはなかった。同時に戦前世代の大半は「親や教師、年長者に口答えするな」「先祖を敬い、家を守れ」など家父長制イデオロギーから脱却できないでいた。
敗戦直後には夢にだに想像しなかった高度経済成長に伴う大量消費社会、そしてIT社会が到来。今や21世紀初年生まれが成人し、戦争体験世代は社会からほぼ消失。未曽有の戦禍と苦難の戦後の日々は遠い歴史の彼方に沈んでしまった。敗戦の悲哀は一掃され、レジュームとしては兎も角、人々の心理における「戦後」は事実上とっくに終焉している。
1970年代に入ると人々は海外旅行ブームに象徴される「豊かな社会」到来により消費活動に心奪われ、「イデオロギーの終焉」が盛んに唱道された。生活保守主義の台頭である。1960年から70年にかけての安保闘争、ベトナム反戦運動、反基地闘争、全国学園紛争を頂点とする権力へ異議申し立てするエネルギーは衰退し、70年代半ばの国労の「スト権スト」への反発を契機に政治への関心は著しく希薄化していった。いわゆる「政治の季節の終焉」である。
日本が再び米国に脅威と受け止められた経済興隆は1980年代にピークに至った。多くの人々が株、不動産などの投資に熱中した。だが1991年バブル経済崩壊とともに熱狂は終焉に向かい、個人も企業も大量の不良債権を抱え、成長神話は崩壊、やがて消費マインドも凍てついた。ここ20年余り深刻な停滞が続く。20年に及ぶデフレ経済は成長をストップさせ、一人当たりの国民総生産(GDP)世界ランキングでは、日本は2000年の2位から2021年には25位に陥落した。2018年に韓国に順位で抜かれたことは日本人にショックを与えた。
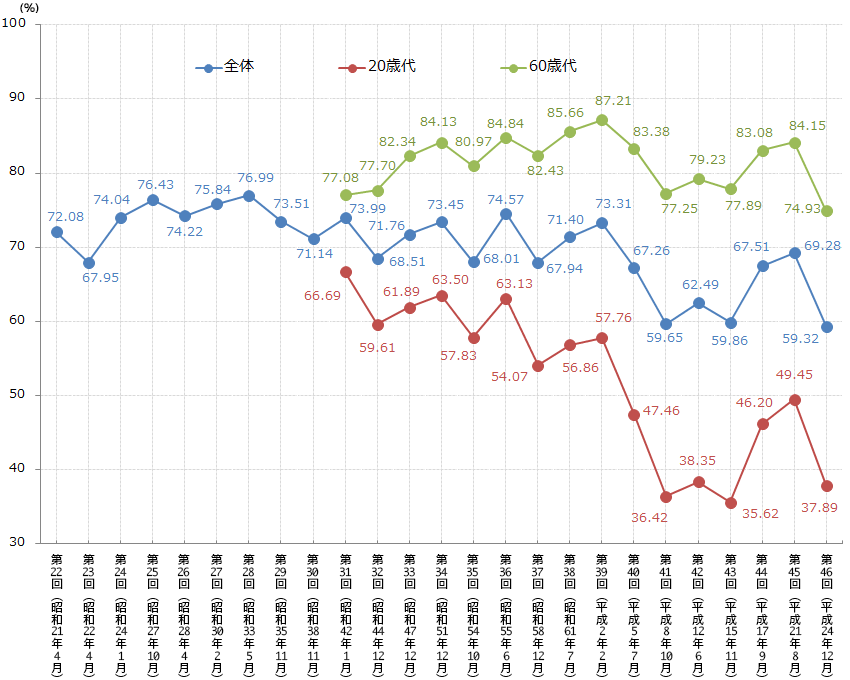 民主主義とは選挙で一票を投じる間接的政治参加だけで到底完結するものではない。とは言え、長期経済低迷による中間層の減少、格差と貧困の拡大にもかかわらず、政治参加への意欲は著しく衰え、最低限の政治参加の目安である投票率は著しく低下した。若年層の棄権が顕著で、総選挙の投票率すら50%を割り込むのは時間の問題とみられる。1946年から1990年まで総じて70%を超してきた総選挙での投票率は1991年のバブル経済崩壊以降70%を割り込み続けている。1996年に初めて60%を割り、2014年には52.66%にまで下落した。参院選挙のそれはとっくに40%台に落ち込んでいる。地方選挙に至っては1951年には90%あった投票率は2019年には知事・首長選、県市町村議会選とも軒並み40%台に低下、30%台への転落も時間の問題となっている。
民主主義とは選挙で一票を投じる間接的政治参加だけで到底完結するものではない。とは言え、長期経済低迷による中間層の減少、格差と貧困の拡大にもかかわらず、政治参加への意欲は著しく衰え、最低限の政治参加の目安である投票率は著しく低下した。若年層の棄権が顕著で、総選挙の投票率すら50%を割り込むのは時間の問題とみられる。1946年から1990年まで総じて70%を超してきた総選挙での投票率は1991年のバブル経済崩壊以降70%を割り込み続けている。1996年に初めて60%を割り、2014年には52.66%にまで下落した。参院選挙のそれはとっくに40%台に落ち込んでいる。地方選挙に至っては1951年には90%あった投票率は2019年には知事・首長選、県市町村議会選とも軒並み40%台に低下、30%台への転落も時間の問題となっている。
これに小選挙区制と圧倒的多数の無党派層の政治アパシー進行が自民党を半永久与党としている。二大政党による白熱した鍔迫り合いと緊張感の欠如が政治への関心を失わせた。自民党は有権者総数の4分の1の支持を得れば政権を維持できる。野党がまったく提携しなければ5分の1でも可能となる。利益誘導型で固定支持層の厚い自民党と大規模宗教団体を母体とする公明党が連立する自公与党は進行する民主主義の崩壊現象を逆手に取るがごとく選挙圧勝の基盤を築いた。近年日本維新の会のような右派改憲勢力の伸びが目を引くがこれは自民補完勢力と見て良い。彼らの背後には日本の権力をハンドルする米ネオコンがいる。
NHKの世論調査によると、1990年代末に支持なし層が50%を超えて圧倒的な「第一党」という状態となった。選挙では支持なし層が結果を左右する存在として一層注目されるようになり、単に支持政党がないというより積極的な意味合いを込めて「無党派層」と呼ばれるようになった。
解説によると、無党派層とは、「単純な政治的無関心派ではなく、政治に関心をもちつつもその関心や期待に応えてくれる政党や政治家をみいだせず、無力感と政治不信を深めている人々」と定義されている。だが間接民主主義の崩壊進行を目の当たりにしながら最低限の政治参加すなわち投票行動すら回避するのは結果として翼賛体制促進への加担となる。現行体制の黙認、不作為是認と解すべきである。
日本ではフランスのマクロン政権に激しく抗議する黄色いベスト運動や米国で起きたウオール街占拠運動のような街頭抗議運動つまり直接的な大規模政治活動は2014年安保法制反対運動を最後に鳴りを潜めた。繰り返すが、事態はなすべきことを行わない不作為がもたらす、権力による露骨な強制のない、一見柔らかな「翼賛現象」とも言える。
翼賛体制についての解説を拾ってゆくと、「要するに、政党もメディアも、軍事的・政治的権力を握っている人間、組織に対して一切批判をせず、彼らの行動についてはひたすら肯定的な姿勢を示し、自身の物理的存在を確保しようとした。」との表現に行き当たった。
この文を以下のように一部変更するだけで現代日本で生まれている新たな翼賛体制を説明できる。
「要するに、日本の政党、メディアは、ごくごく一部を除き、日本の軍事的・政治的権力を掌握している米国に対して一切批判を行わず、米国の行動についてはひたすら肯定的な姿勢を示し、自身の物理的存在を確保しようとしている。」
同様に、「『翼賛体制』というのは、狭い意味では、日本の太平洋戦争下における一国一党組織である大政翼賛会を中心に、軍部の方針を無批判に追認し、国民を戦争に総動員した体制のことである」との説明がある。これを次のように言い換えてもさして違和感はなかろう。
「現代日本の翼賛体制というのは、野党の小党分立と相互対立、ワシントンの介入により1955年保守合同で結党された自由民主党の半永久的与党化、野党の支持母体であるはずの労組の自民党政権接近、労働組合、市民運動や学生運動など対抗勢力の著しい衰退によって形成された一国一党に近い政治状況を中心に、日米安保条約・地位協定を礎とするワシントンの方針を無批判に追認し、国民を対中露冷戦やウクライナをはじめとする米国の代理戦争支持へと総動員している体制のことである」
■新翼賛体制下の心理と行動
新たな翼賛体制の構造は、疑似主権国家日本の政財官+メディアとその上に聳え日本の権力層を思うままに動かす実質統治者である米国の支配層との二重権力状態によって成り立っている。これが大戦中の総動員・翼賛体制との構造上の違いである。とは言え、せんじ詰めれば天皇大権国家への翼賛が覇権国アメリカへのそれに置き換わったにすぎない。
実際それを担う日本人の心理と行動に戦前・戦中のそれと根本的な変化はみられない。日本は依然人々が基本的に個を抑え、組織の意思を適切に感じ取ってそれに同調し、協調態勢を組むことで所属集団内での地位と昇進が保証される集団主義社会である。戦中にピークに達した戦前の絶対服従型から戦後は一定の個人尊重と柔らかさを内包する「空気を読む(KY)型」に転換したとも言えるものの、依然として上意下達の権威服従・自己犠牲の意識が社会に根強く蔓延っている。長期経済低迷はこの風潮高揚の「カンフル剤」となった。
戦後の日本型経営システムは1940年戦時総力体制を受け継いでおり、これが日本の戦後復興と高度経済成長の原動力となった。温存されたこのファッショ型総力体制を米国が脅威と受け止め解体を図ったことは本ブログでは再三言及してきた。注:2021年11月29日掲載記事「日米安保破棄と対米自立を再び争点に(その1) 近代日本第三期考2」などを参照されたい。
終身雇用、年功序列、企業内組合を「三種の神器」とし、官僚主導で各業界を丸ごと保護する護送船団方式で守られ、膨大な下請け系列企業を傘下に収めて圧倒的な価格競争力を獲得し、金融機関(メインバンク)を核とする株式持ち合い制の巨大企業集団によって構成される日本型システム。これはここ30年で米国の計画通り弱体化した。だが有力企業の上位株式保有者に米国資本が多数進出し、非正規雇用が浸透しても、労働現場には陰湿で非人道的な慣行とシステムが残された。
日本型の雇用システムは変容した。派遣労働の浸透とともに1990年には雇用全体の約20%だった非正規雇用は30年後の2020年には約40%にまで拡大。雇用が不安定となったにとどまらず、労働基本権である団結権、団体交渉権、ストライキ権を行使して給与アップを勝ち取ろうとする意欲も衰退、所得も縮小してきた。一カ月当たりの勤労者世帯の平均実収入は2000年の約56万円から2011年には約51万円へと減少。2022年1-3月期の1カ月平均は51万円を割り込み、直近の同5月単月では48万円台へと下落した。(注:数字は総務省統計)
加えて、規模の大小を問わず、長時間過重労働、違法労働、パワーハラスメントによって就労者を使いつぶし、続々と離職に追い込むいわゆるブラック企業の存在が社会問題となった。その大半は過酷な労働の見返りとしての長期雇用保障や手厚い企業福祉を付与しない上、指揮命令が強固で、経営者、上層部が強大な権力を握っており、従業員が団結権を行使して労組を結成するのを拒んでいる。
労働者を死に追い込むブラック企業上位には日本の有力企業が並んでいる。労働組合役員やNPO法人の代表、作家、弁護士らで運営していた「ブラック企業大賞企画委員会」が2012年から2019年までに発表したブラック企業大賞受賞には三菱電機、日立製作所、電通、セブンイレブン・ジャパン、大成建設、ヤマダ電機、東京電力などといった著名な大手企業が名を連ねた。このほか、トヨタ自動車、KDDI、関西電力、パナソニック、大和ハウス工業、ヤマト運輸、吉本興業、野村不動産、スルガ銀行など多数の著名な大企業がノミネートされた。
曲がりなりにも終身雇用制が残り、年功賃金、健康保険組合の存在と医療厚生制度の充実、退職後に備えた老齢年金加入、社内預金など企業福祉が保証されている日本の大企業がブラック企業と「認定」されるのは、企業運営の根底に戦時総力体制が継承されているからにほかならない。従業員の心理と行動に重くのしかかり、それを縛るのは戦陣訓を戦後に後継した「一社懸命」「全社一丸」の企業ファシズム精神である。戦後は極端なスローガンは減ったが社風や職場の不文律となって日本の企業社会を覆っている。
■鬼十訓と稟議制
軍人勅諭を受け継いだ「生きて虜囚の辱を受けず」との戦陣訓の一節が日本軍兵士に対する玉砕の強制ばかりか沖縄戦などでの民間人の集団自決をもたらしたと問題視されてきた。太平洋戦線や中国やアジアの戦地からの帰還兵たちによると、敵を殺すことと死ぬことは同価値であると叩き込まれ、上官に「死んでも大和魂は残る。死んだら魂で敵を殺せ」と言い聞かされた。
「ビジネスの現場は戦場だ。負ければ会社は潰れ、我々は死ぬ。死にたくなけば競争に勝つしかない」。
1971年。日立製作所に入社して当時の本社機電営業本部官公需部に配属され、東京都発注の下水道処理プラント入札を巡る受注合戦の現場に身を置いた新米企業戦士は「談合罪での逮捕も恐れるな」と暗示して憚らない部長の訓示に驚愕した。日本の会社で働くとはまさに死と向き合う「常在戦場」と心がけることだった。
中小企業になると体罰が加わる。1979年。ある日本の地方都市の小規模ビジネスホテル前の駐車場。職種は判然としなかったが、出張販売チームのリーダーは朝礼で5、6人の部下をこう強迫した。
「今日契約がひとつも取れない奴には夕飯は食わせない。わかったな!」
出張部隊長は古参兵、平社員は新兵、会社は軍隊であった。殴る、蹴るの暴力は日常茶飯事だったはず。
一般的には、これらの事例は天皇制ファシズム体制の下で教育され、働き、軍隊を体験した戦後第一世代の父親世代が社会の中核で活動した1970年代までに起きたことと見なされがちである。だが戦後教育を受けた団塊の世代や戦後第一世代が企業で中核的役割を果たすようになっても事態は改善しなった。バブル経済破たん後の長期景気低迷が非正規社員、新入社員、上司や組織的指示に従順でない者への解雇を頂点とするハラスメント、迫害の度を高めた。
典型的事例が2015年末に起きた広告業界最大手電通の新入女性社員過労自殺事件である。この社員は同年4月の入社後、本採用後の10月以降に仕事量が急増。遺族側の推計によると、1カ月の時間外労働は過労死ラインといわれる80時間を大幅に超える約130時間に達していた。
自殺した女性社員は本採用後に休日にも社員の6割が出勤する異常さに驚くメモを残し、その後、自殺直前には「何日も寝られないくらいの労働量はおかしすぎる」、「土日も出勤しなければならないことがまた決定し、本気で死んでしまいたい」、「1日20時間とか会社にいるともはや何のために生きてるのか分からなくなって笑けてくる」などと書き残していた。過労に加え、上司によるパワハラ、セクハラが続いたとされる。翌2016年6月、労働基準監督署は「長時間労働によるうつ病発症が原因」として労災認定した。
電通社員の過労自殺認定は過去にもあり、この事件を機に厚労省特別対策班が本社や地方支社を抜き打ち調査すると、違法な長時間労働、労働時間の過少申告強要、かつての在勤中の病死扱いが過労死だった事例などが相次いで判明した。違法な時間外労働が全社的に常態化しており、東京労働局特捜班は強制捜査に切り替え、電通本社と全国の3支社に労働基準法違反の疑いで家宅捜査、電通と女性社員の当時の上司を労働基準法違反の疑いで送検し東京地検は起訴に踏み切った。当時の電通の社長は引責辞任に追い込まれた。
 この際、問題となったのが「電通の鬼十訓」である。10の訓示中5番目の「取り組んだら放すな、殺されても放すな、目的完遂までは」が特に論議を呼び、電通はこの事件を機に社員手帳から十訓を削除した。電通の社風を作った十訓は戦中派の四代目社長吉田英雄(1903 - 1963)の手による。企業経営者にはこれを高く評価し、座右の銘としている者も多い。
この際、問題となったのが「電通の鬼十訓」である。10の訓示中5番目の「取り組んだら放すな、殺されても放すな、目的完遂までは」が特に論議を呼び、電通はこの事件を機に社員手帳から十訓を削除した。電通の社風を作った十訓は戦中派の四代目社長吉田英雄(1903 - 1963)の手による。企業経営者にはこれを高く評価し、座右の銘としている者も多い。
確かに、その他の訓示、「仕事は先手先手と働きかけていくことで、受け身でやるものではない」、「大きな仕事に取り組め、小さな仕事は己を小さくする」、「難しい仕事を狙え、そしてそれを成し遂げるところに進歩がある」、「計画を持て、長期の計画を持っていれば、忍耐と工夫と、そして、正しい努力と希望が生まれる」などには説得力もあり、日本の経営者が朝礼などで社員に訓令する際好んで引用しそうな文句である。
だが、企業はモラル教育の場ではない。人生観や価値観は個々人が私生活の場でそれぞれ培うもので、企業トップが社員に押し付けるのは越権行為だ。社員手帳の冒頭に記す十訓は上意下達の集団洗脳手段と言える。この種の「戦後版戦陣訓」は日本企業の至る所にはびこり、会社組織を超えて教育の場にも入り込み社会風土とさえ化している。「取り組んだ仕事は殺されても放すな」は「殺されても魂で戦え」という戦場での訓示と重なる。
戦中精神はこのようにして生き続け、「マイホーム主義は論外」、「寝食を忘れ働け」との企業戦士への訓示となる。1980年代には大手製造業の幹部社員さえ「利益なき繁忙」を自嘲し、「24時間働けますか」とのキャッチコピーが流行った。利益を最小化、時には度外視してまで国内外市場でのシェア拡大競争にしのぎを削る、「一丸火の玉」を掛け声とする集団主義は米欧企業からは1930年代の日本製品排斥で謳われたソーシャルダンピング(極端に低位な賃金水準や劣悪な労働条件を利用した不当廉売=社会的投売)の再来と恐れられた。彼らが日本人の企業戦士ぶりを「ウサギ小屋に住む仕事中毒のエコノミックアニマル」と揶揄したのはいまだ記憶に新しい。
日本で官民を問わず長時間労働をもたらし、上意下達の権威的抑圧を生み、組織を無責任の体系としているのが稟議制度である。
明治期以来、日本の行政組織や企業経営における意志決定は、末端職員による起案文書(稟議書)を、関係官(者)に順次回議してその印判を求め、上位者に回送して最終決裁者に至る稟議制度が採用されてきた。決定権も指導力ももたない末端職員が起案した稟議書は関係課部局の責任者が個別に審議して積み上げて行き、長い過程を経て承認権限のある組織長(大臣や社長)に上げられる。稟議の過程に長い時間を要し、最終責任は組織の長にあるが、長は起案の指示を逐一行わないので内容にうといまま「めくら判」を押しやすい。末端にも最高位にも決定権が奪われている。「無責任の体系」といわれるのはこのためだ。
- さらに問題は起案文書が順次回送される各段階つまり課長、部長、局長、大臣官房長(担当役員)、次官(副社長)といった事務レベルで拒否されて書き直し、修正を命じられ、何度も起案者に戻ってくることだ。特に役所でこの傾向が著しく、起案者、課長(課長補佐)、部長(部次長)、局長(局次長)の間を際限なく文書は行き来する。霞ヶ関官庁街の地下鉄駅には未明の最終電車に大勢の専門職職員(ノンキャリ)が殺到する。かつて通商産業省と呼ばれた経産省職員は「通常残業省」と自嘲していた。
- ■静かな翼賛:生活保守主義と怒りの抑制
- 戦後復興、高度経済成長と1980年代にピークを迎えた日本の経済力は1990年代に始まり2000年以降著しくなる衰退過程に入った。長期経済衰退という新たな敗戦によって総力体制は権利はく奪への総動員にかわった。選挙権、団結権、スト権の放棄、既成メディアの権力者への忖度と委縮に絡む表現の自由の抑制と放棄、 集会デモへの無関心ー。民主主義の諸権利はないがしろにされてしまった。政治や社会への批判と怒りは抑制され、集団的うつ病が発症、社会全体に蔓延している。
- そこには1986年労働者派遣法を嚆矢に、日本社会党の解体につながる、国鉄、電電公社、専売公社をはじめとする公営企業民営化とこれに並行した労働戦線統一という名の「連合」の誕生、裁量労働制導入、非正規労働の増大、労組組織率低下とストライキの激減といった新自由主義政策の導入結果があり、新たな翼賛体制を下準備した。中曽根内閣(1982-1987)の唱えた「戦後政治の総決算」とは復古型保守主義への回帰と米国発新自由主義の導入というアマルガム(混合物)によって自社二大政党制のいわゆる1955年体制の解体を図るものであった。
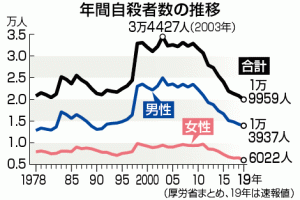 1998年から連続12年間、日本では年間自殺者が3万人を超える未曾有の事態を招いたのは記憶に新しい。自殺率、実数ともに先進7カ国の中でも群を抜いている。日本政府による19世紀末以降の統計を見ても、この期間の数字は突出しており、戦後達成したとされる豊かな社会が決して人々を幸せにはしていないことを示している。
1998年から連続12年間、日本では年間自殺者が3万人を超える未曾有の事態を招いたのは記憶に新しい。自殺率、実数ともに先進7カ国の中でも群を抜いている。日本政府による19世紀末以降の統計を見ても、この期間の数字は突出しており、戦後達成したとされる豊かな社会が決して人々を幸せにはしていないことを示している。- 上記のように企業においては総力体制は生き続ける一方、私的生活ではその反動として分断された多くの人々がアパシーと気分障害・鬱状態、最悪のケースとして自死へと動員されている。人々は雇用が不安定となるばかりの働く現場で抑圧、苦悩を組織的に跳ね返すすべを失っている。電通事件でも、会社側は恒常的に労使協約(三六協定)で決めた残業時間の上限を超さないよう勤務時間を過少申告するよう指示していた。ところが労組の組織率が低すぎて司法判決は三六協定違反を違法と認定できなかった。
- 戦中の強制による翼賛体制に代わって生まれつつあるのが政治参加忌避型の静かな翼賛体制だ。大企業の労働組合は事実上ストライキ権を放棄して賃上げ要求を自粛。このため労働運動に敵対してきた与党自民党政権が経済団体に賃上げを斡旋する前代未聞の倒錯した現象が起きている。トップ企業に属する労働貴族で組織する御用組合が”連帯する”ナショナルセンター「連合」は反共の旗を掲げ自民党と一体化し「産業報国会」へと向かっている。
- 多くの勤労者は団結権を放棄し、労組組織率は1948年の55.8%をピークに2019年には16.7%となった。日本特有の企業内組合と労使一体化の一層の進展は「労働運動やそれへの深入りは会社での地位、昇進を危うくする」との生活保守主義によって促されている。日本の伝統的同調主義はベニート・ムッソリーニらファシストが国家組織に経営者や労働者の代表を組織して生まれた「国家コーポラティズム」の形へと進んでいる。
- ■依然ワシントンは日本を警戒
- 日本の権力の上に君臨する米国の支配層は人々の怒りが日本の弱体化を図ってきた米国に向かないよう細心の注意を払っている。中国に加え、ロシアが今にも侵攻してくるような脅威感の創出はウクライナ危機の宣伝で奏功した。中露、北朝鮮といった外敵への恐怖扇動プロパガンダ、さらには韓国への嫌悪を煽り、「すごいぞニッポン」といった類の偏頗なナショナリズムの高揚工作はIT産業を介して日々時々刻々間断なく行われている。
-
ワシントンが最も恐れているのは米国自ら作った「必要最小限の実力組織」でありながら、今や世界5位の軍隊となった自衛隊における反米感情の爆発である。警察予備隊、保安隊を経て1954年自衛隊発足に際し元陸海軍佐官クラスが幹部ポストに多数採用されており、自衛隊には旧日本軍の血脈が今もしっかり生きている。
-
日本の戦後保守支配層とともに自衛隊幹部層にはかつて「必ずアメリカを見返してやる」との情念が蠢いていた。このため防衛庁キャリア官僚、自衛隊幹部は在職中、あるいは退職後に米国の有力大学への留学や研究機関でしかるべきポストを与えられ招聘されている。こうして日本の新国防エリート層はイデオロギー上も金銭的にもワシントンのインナーサークルに取り込まれている。
-
ただし、軍人間での価値観の共有が本音ベースでどこまでできているかは疑わしい。航空自衛隊トップが「日本は侵略戦争をしていない」と正面から東京裁判を否定した田母神論文事件(2008年)はこの疑念をあからさまに浮上させた。
-
ここ20年の在日米軍再編と自衛隊の米軍との一体化の進展、米軍横田基地への米日両軍統合司令本部「共同統合作戦調整センター」(BJOCC)の設置は自衛隊を米軍に直接指揮される補完部隊とし、米国がその動きを逐一監視して暴走を封じるためとも言える。
皇国史観を克服しきれない日本人と日本社会に潜伏する総動員・翼賛体制へと向かいやすい体質は米国の支配層がドイツ、ロシア、中国と並び最も警戒しているものである。
-
「日米安保条約は日本軍国主義を封じ込める瓶の蓋」との米国側の発言は言葉以上に重い。
